
きらびやかなアントルメ、麗しく純白のコックスーツ、美しいショーケースetc.作り出すお菓子と世界観は、憧れる人も多い「パティシエ」という職業。子どもたち、とりわけ女子の「なりたい職業」では、上位常連のこの職業。そんなキラキラして見える世界とは一変し、近年多くのニュースやメディア、元パティシエのSNSから発信される「重労働」「過酷な世界」という、重々しい言葉の数々も。「現代のパティシエ」を代表する超一流の職人たちに、お菓子に対する生き方、覚悟、そして現代の洋菓子界へ思うことを、深く、さらに深く、奥底に眠る“アティチュード”を取材。パティシエたちが語る“仕事観”と“洋菓子”への想いを、新連載としてお届けします。
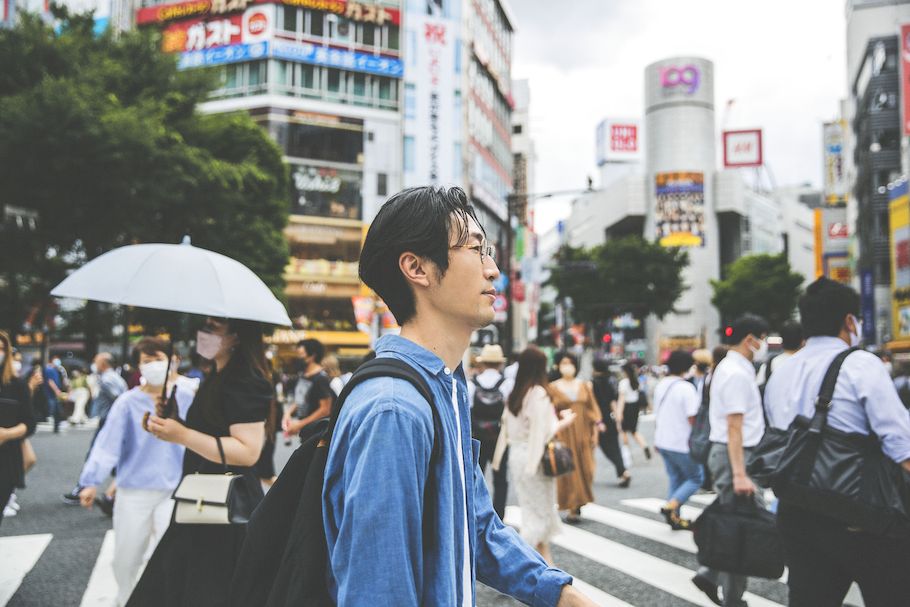
「僕はそもそも実家が、福井で230年以上続く歴史ある和菓子屋。長男として生まれたこともあり、学校の先生や友達からも“将来継ぐでしょ”といわれて、育ってきました。
“敷かれたレールがあるような感じ”がすごく、すごく嫌だった。中学生なりに考えて、勉強めちゃくちゃできれば、その道が変わるんじゃないかと思い“僕、和菓子屋継ぎません。大学へ行きます”と。その時の父は、大反対することもなく、逆に新しい道を選んだ僕を認めてくれました。

「実は大学生時代、妹と同居していて。大学3年生のときに、妹が“これめちゃくちゃおいしいから食べてみて”と持ってきたお菓子がありました。甘いものを毛嫌いしていて、和菓子屋から逃れようとしていた僕を知っている妹が、お菓子を持ってくること自体が珍しくて。
それに当時は、洋菓子のレベルがそこまで高くなかった。そういうこともあって、なんで持ってきたんだろうと疑問に思いながら食べたんですが、それが僕の人生をいい意味で狂わせたお菓子、そう尾山台にある「オーボンヴュータン」のケーキでした。

ひと口食べて衝撃を覚えて、“なんじゃこりゃ、フランス菓子ってすごいな”と感動したのを、今でも覚えています。
もともと学生時代は、学校では“はぐれメタル”と呼ばれるぐらい、学校には行かなくて、月30万ぐらい稼ぐほど数多くのをバイトをしていたんです。飲食店が楽しくて、とくに料理を学ばせてもらえたお店では“作ること”の楽しさを学んで、何かを作ることが、自分には向いているのかなと思っていました。そんなタイミングで、この“オーボンヴュータン”のケーキを食べた。これが“はじまり”です。」
「ちなみに、大学卒業後は東京製菓学校へ。就職の実績をみると、東京製菓だけオーボンヴュータンと書いてあったので、入りました。」

「父親は、高校卒業して老舗で住こみで働いていたこともあり、父から聞くその当時の話は“まじか”と思う話ばっかりだったので、覚悟はできていました。それに昔から、父親が職人として、声を荒げて叱る姿は毎日みていたので。パティシエを選んでいる時点で、厳しい覚悟を持っていたのかもしれません。
オーボンヴュータンでの生活は、予想通りの世界でした。学校を卒業するときは、まわりの先生から“本当に厳しいぞ”と言われて心配されましたが、僕は“どうせいくなら、一度行ってしまえば後が楽だろ”ぐらいな感覚でした。」
「初日からすごい緊張感でしたね。厨房が殺伐としていたし、とりあえず早く手を動かしている。雑音という雑音は、仕事の音だけ。この空気感、これは全然嫌ではなかったんです、すごく刺激的でした。
10秒でも手が止まったらアウト。次何しようと思った瞬間、罵声が飛ぶ。そんな環境で、“この作業が終わったら”の選択肢を5個ぐらい考えていました。先輩後輩関係なく、仕事の奪い合い。できたもの勝ち。すごい楽しかったですね。」

「やっぱり、僕はこの仕事が好き、とことん好き。厳しさを乗り越えたあとにある、達成感と人に喜んでもらえる幸せが何よりもたまらなくって。だって、1年に1回の誕生日、人生の節目となる結婚式のものを、僕が作れるということが何よりも原動力となっています。」

「原動力、ということでいうともう一つあります。コロナ禍で、2カ月間お店を閉めざるをえなかったことがありました。お店のマネジメントをしながら、後輩の子たちには週に1回出てきてもらって、頭でいろいろなお菓子を考えてもらうなどして下の子たちのモチベーションは保ててはいたんですが、肝心な自分のモチベーションを維持しようかと思ったときに難しかったんです。
忙しくしていた日々から、ぽっかりと生まれた空白の時間。試作する時間にすればいいや、次のクリエイティブにあてればいいやと思っていたのに、再開のめどがたたず、どうなっちゃうんだろという不安があって、全然アイデアが生まれてきませんでした。食べ手が想像ができなかったんですよ。」
「どうしようと思ったときに、インスタグラムでお菓子のレシピをあげてみようと、一つの投稿がきっかけになりました。びっくりするほどの反響をいただけて、もう1回やってみようと思ったら反響がさらに大きくなり、毎週考えるのが楽しくなってきたんです。“パティシエってこういったこともできるんだ”、“みんなの役に立てるんだ”というところに気づくことができました。
お客さんとのSNSを通じてキャッチボールも楽しくて、“バターをやわらかくすると、うまく焼けますよ”などと作り方のアドバイスをすることも。そんなやりとりも刺激的で、実際お店の営業が再開してからも、Instagramを通じて初めて来店してくれた方もいました。僕にとって原動力は、食べてなんだなと改めて気づいた瞬間でした。」

「地元の福井に戻って、お菓子を作っていくことです。地元に愛され、地元を応援するそんな新しい挑戦を目指したいです。目標としては、2年後を考えています。今からとてもワクワクしていますね。」
「どちらかというと、今後は洋菓子とか和菓子とかフランス菓子とかの垣根をなくした、僕のお菓子をお届けしたいです。今まで培ってきたお菓子のフィルターを通して、新しい価値を作っていけたらと考えています。」

「“菓子職人”です。和菓子屋でもパティシエでもなんでもいいけれど、共通するのはお菓子をつくる職人であるということです。」
職人という言葉は華やかな言葉に聞こえますが、やはりパティシエというのは職人であって、労働者です。もちろん、表現者でもあるけど、身を粉にして、一生懸命やっている。そこっていうのは職人の美しさでもあり、僕の哲学でもあります。」
「僕は、森さんの話をぜひ聞いてみたいです。あの美しいパフェのフルーツのカットの仕方、見せ方、それだけでも、どれだけの職人魂がつまっているか。そして“ラトリエ・ア・マ・ファソン”という、あれだけの世界を作り上げる、あの人の考え方を、若い子がすごく参考になると思いました。森さんは“僕はパティシエじゃないしなぁ”というかもしれなけれど、お菓子のこだわり、情熱はすさまじいものがあります。ぜひ聞いてみたいですね。」
Profile
昆布智成 Kombu Tomonari
1981年 福井県で230年の歴史を持つ和菓子店「昆布屋孫兵衛」の長男として生まれる
2004年 日本大学商学部卒業
2006年 東京製菓専門学校卒業
同年 東京に拠点を置きオーボン・ヴュータンにてフランス菓子の基礎を習得
その後 「ピエール・エルメ サロン・ド・テ」入社
2011年メープルスイーツコンテスト入賞の経歴を持つ
2012年 渡仏し、南仏のパティスリー「リエデレ」でMOF(国 家最優秀職章)に師事しガトー・グラッセや地方菓子を学ぶその後、パリでは2つ星レストラン「ラトリエ ・ド・ジョエル・ロブション」でデセールを担当
2015年 アン グラン スーシェフ パティシエとして入社
2019年4月よりシェフ パティシエに就任

クリーム太朗
ウフ。編集長
編集責任者。ショートケーキ研究家として、日本全国のケーキを食べ比べる。自身でも、ケーキやチョコレートの製造・販売を目指すべく、知識だけではなく実技も鍛錬中
Photo/Yoko Nakata Writing/Cream Taro Direction/Kana Tsukumo
注目記事
